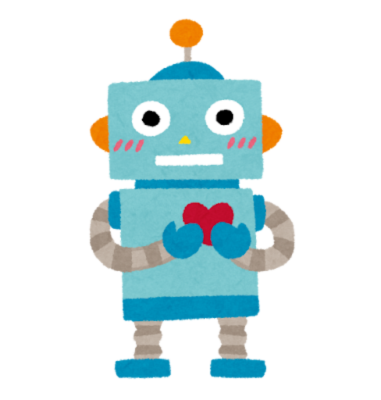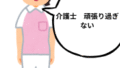介護士が認知症ケア専門士試験に落ちて
私は先日、認知症ケア専門士の試験を受けましたが、結果は不合格でした。恥ずかしい事に 3回目となります。(この資格は4つの分野に分かれてまして。「認知用ケアの基礎」「認知症ケアの実際Ⅰ:総論」「認知症ケアに実際Ⅱ:各論」「社会資源」の4つのうち 3つは受かっているのですが 「社会資源」は合格出来ず。
「社会資源」は、私は非常に、苦手だと感じました。簡単に説明します。
医療保険制度や介護保険制度など、社会保障の内容を詳しく学ぶ内容です。苦手で理解出来ていません😭
ただ、資格は取れなくても「認知症を学ぶことの面白さ」や「現場での実践につながる知識」を得られたのは大きな収穫です。
認知症の方との対応で大切にしていること
介護施設の現場で、私が実際に心がけているポイントを話します。
1. 観察力を磨く
認知症の方は、言葉にできない不安や困惑を表情や動作に出されることがあります。
・同じ動作を繰り返す
・表情が急に変わる
・動作が途中で止まる
こうしたサインを読み取ることが、事故予防や安心感につながります。
2. 声かけと環境調整
「できないこと」に注目するのではなく、「できている部分」を認める声かけを意識しています。
声のトーンを気をつける(声の高さ・大きさ・速さ)
また、雑音や人の出入りが多い環境では注意が散漫になりやすいため、環境を整えることも大切です。
3. 尊厳の保持
時間がかかっても、その人なりの方法で行動できるように待つこと。
羞恥心に配慮し、声かけのトーンや言葉選びにも気をつける。
「待つケア」こそ、尊厳を守る第一歩だと考えています。
介護士47歳で学び続ける意味
私は47歳。決して若いわけではありません。
「今さら勉強しても意味があるのか」と思うこともあります。
しかし、学びを現場で活かせたら少しの知識ですが 利用者様にやさしく接する事が出来ます。
資格に合格することは目標の一つだったですが、知識は宝として
学んだ知識を日々のケアに活かし、「一人ひとりに合った関わり」を追求することこそ、学びの価値だと思います。
まとめ
認知症ケア専門士の資格には届きませんでした。😢
ですが、認知症ケアの学びは続けていきます。
資格の有無に関わらず、観察力・声かけ・尊厳の保持といった視点を大切に、日々の現場に活かしていきたいと思います。
最後まで読んでいただき ありがとうございます。よかったら、また記事更新もチェックしてみてください。また、遊びに来てください。
① 書籍の紹介(楽天ブックス)
記事の中で「参考になった本」として紹介します。
| 2024年版【1次試験対応】この1冊でらくらく合格認知症ケア専門士 テキスト&予想問題集 [ 永嶋昌樹 ]価格:3080円 (2025/8/26 22:44時点) 感想(0件) |
私が認知症ケアを学ぶ中で参考になったのがこちらの本です。