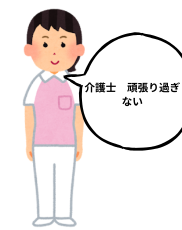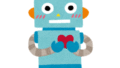介護の仕事が好きだけど、給料が上がらない。
介護士として働いていて、利用者さんとお話したり、笑顔を見られる瞬間は本当にやりがいがある仕事です。
でも現実は、基本給が低く、将来に不安を感じてしまうことも多いです。
一方で、「介護報酬」や「処遇改善加算」という制度があるはずなのに、現場で働いていても給料が上がっている様に感じない。生活が楽にならない。
「本当に私たちに還元されているのだろうか?」
「ごまかされているのでは?」
そんな疑問ややりきれなさを抱える職員も少なくないと思います。私なりに 調べてまとめてみました。
介護職の給料はなぜ低いのか
介護職の給料が低い大きな理由は、介護サービスの料金(介護報酬)が国によって決められているからだそうです。(;´д`)
施設は自由に値段を設定できず、限られた報酬の中で人件費・建物・光熱費などをすべてまかなわなければなりません。(知って こりゃ大変と少し考えさせられました)
そのため、基本給を上げる余裕がなく、「処遇改善加算」という手当で調整するケースが多いのが現実です。
結果として、基本給が上がらないまま → ボーナスや退職金も少ない → 将来に不安を感じる、という状況。
介護報酬とは?
介護報酬とは、介護施設や事業所がサービスを提供したときに、国や自治体から支払われるお金です。
利用者さんは1〜3割を自己負担し、残りは介護保険から支払われます。金額は国が決めていて、5年ごとに見直されます。
また、職員の処遇改善を目的に「処遇改善加算」という仕組みもありますが、実際にどう配分されているかは施設次第です。
そのため、職員が恩恵を実感しにくいことが多いのです。
なぜ職員に反映されにくいのか
介護報酬や加算はまず施設の収入になります。そこから建物の維持費や備品、光熱費をまかなうため、必ずしも全部 介護職員の基本給に回るとは限らないようで
※施設によってですが 介護職員だけじゃなく 看護や事務員などにも割り振る所もあります。兼務で介護をしている場合は含まれる様で なら 施設で人員が足らない時 全体で助けましょうよと 叫びたい!!!
多くの施設では「加算分」を一時金や手当として支給しており、基本給は変わらないままです。
そのためボーナスや退職金に反映されず、現場の職員にとっては「やりがいはあるけど生活が苦しい」というやりきれなさにつながっています。
現場から見える“ごまかされ感”
職員が退職すると、残った職員に割り振りが回り、1人あたりの業務が増えます。
しかし介護報酬は「利用者数やサービス量」で決まるため、人が減っても施設の収入は変わらないのです。
つまり、職員だけが疲弊していく悪循環が起きています。
さらに介護施設には「人員配置基準」があり、基準を満たさないとペナルティがあると。
- 介護報酬の加算が取れなくなる
- 行政から改善命令を受ける
- 最悪の場合、業務停止や指定取り消し
このため書類上は「基準を守っている」と見せても、実際には現場で過重労働が起きていることもあります。
職員からすれば「制度はあるけど、現場はごまかされている」と感じる瞬間が多いのです。人が足らないから休んだら周りや利用者が困るからなど、無理をして心も体もダメになってしまい離職してしまう事は 悲しいし悔しいしもったいないと考えてしまいます。
まとめ 〜介護報酬と給料の現実〜
介護報酬の仕組みは「職員の処遇改善」を目的としていますが、現場にいるとその効果を実感しにくく、むしろ「ごまかされている」と感じてしまいます。「バカにするんじゃねぇ」と私は叫びたい!!
私は利用者さんとの交流は大好きですが、生活の柱を介護職だけに頼るのは危険だと思いました。
だからこそ、介護に依存しない働き方としてブログを始めました。
介護のやりがいは大切。
でも同じくらい、生活の安定や将来の安心も大切です。
これからも介護現場の経験を活かしながら、別の収入の柱を作り、自分らしい働き方を目指していきたいと動き出しています。同じ介護の仕事をしている方も 知らないはもったいないし やらないももったいないと思います。人生一度きり 少しでも楽しんで過ごせる人生になる様、最後まで読んでいただきありがとうございました。